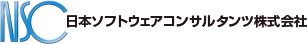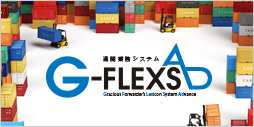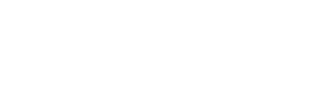パッケージソリューション
- トップページ
- サービス紹介
- パッケージソリューション
- 海貨用語集

海貨用語集
A
AWB(Air Waybill)
貨物を航空機で運送する時に航空会社が発行する貨物受取証をいい、航空貨物運送状ともいわれる。その様式は国際運送協会(IATA)の貨物運送会議で決定され、加盟航空会社で使用されている。航空積荷受取証は船荷証券とは異なり、単なる貨物運送状であって、有価証券ではなく、また、原則として記名式であり、非流通性である。
A / N(Arrival Notice)(貨物到着案内書)
貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Notify Party(着荷通知先) 宛に貨物の到着を通知するための書類。一般的には運賃請求書(Freight Bill)を兼ねることが多い。
ASEAN(Association of South East Asian Nations)(東南アジア諸国連合)
1967年バンコクにおいて5カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(これらを原加盟5カ国という))によって設立。 その後、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマーと続き、1999年にカンボジアが加盟して地域全体を包含する「ASEAN10」が完成した。当初は、ベトナム戦争や中国の国連加盟などの政治情勢の変化に対して、「平和、自由、中立」を唱うなど政治・安全保障的な側面が強かったが、現在は政治・経済の安定以外に域内の経済成長、社会・文化的発展の促進も目的としている。
B
Before Permit(輸入許可前取引)
輸入貨物は、輸入の許可を受けた後でなければ国内に引き取ることができないが、特別な理由がある場合には、税関長の承認を受け、関税等の額に相当する額の担保を提供することにより、輸入許可前に貨物を国内に引き取ることができる制度のことである。
Berth(バース)
荷役を行う港湾施設。船舶が着岸し荷役を行う場所のことをいう。岸壁や桟橋がそれに当たる。岸壁と桟橋の違いは、岸壁は海底まで埋め立てられているものを言い、桟橋は支柱のみのものをいう。
B / L (Bill of Lading)(船荷証券)
運送人が荷送人との間に於ける運送契約に基づいて、貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類で、荷送人の請求によって運送人が発行する。 B/Lは次のような性格を有している。(1)物品の(海上、複合)受取証、運送契約書 (2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証 (3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場合に必要となる、“荷”を表象する有価証券。
Booking(船腹予約/船積予約)
船会社、航空会社に貨物の運送依頼の予約をすること。通常、ある特定の航路に就航する船舶又は航空機について、ある仕向地までのスペースを確保する意味で用いられる。
Bonded area(保税地域)
輸出入貨物の通関手続をとる場合に、貨物を一時税関の監督下に置く必要から設置された地域で、同時にまた、外国貨物を課税保留、輸出入手続未済のまま蔵置できる地域でもある。保税地域には、関税法の定めるところにより、「指定保税地域」「保税蔵置場」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」の5種類がある。
C
Cargo(貨物)
関税法における貨物とは、有形的財貨で移動するものをいう。関税法上の輸入対象となる貨物は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により、公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物である。
Cargo Manifest(積荷目録)
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B / LNO.個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関に積荷目録を提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告は積荷目録が税関に提出された後に行われる。
Carrier(運送人)
陸上・湖川・港湾において物品、または旅客の運送を行うことを生業とする者のことをいう。
Certificate of Origin(原産地証明書)
貨物の原産地(生産地又は製造地)を証明した公文書。輸入者が輸入貨物に関税が賦課される際に国定税率より低い協定税率の適用を受けるため、輸入国のダンピング防止や為替管理などに使用される。輸出者が作成し、輸出国の商工会議所、政府機関及び輸出国にある輸入国領事館で証明を受けることができる。
Commercial L / C(商業信用状)
輸入者のために輸入者の取引銀行が自己の信用を提供し、一定の条件のもとに輸入者が自行又は取引銀行若しくは輸入者宛に為替手形を振り出した場合には、その手形の引受け、支払い、買取りを自ら保証するか、又は取引銀行にその手形の引受け、支払い、買取りを行うよう授権する証券のことである。
Consolidation(混載)
ひとつのコンテナに2種類、2荷主以上の貨物、複数の荷主から集荷した貨物をまとめて積み合わせることを混載という。
Consolidated Cargo(混載貨物)
輸送の一単位(貨物、トラック、コンテナ、パレット等)を構成するに足らない小口貨物(LCLCargo)を集めて、一つの輸送単位となっている状態または貨物を指す。
Consolidator【混載業者】
「コンソリ」とは「混載」の意味だが、港湾用語としては混載業者を指すことが多い。複数の荷主のLCLcargo(小口貨物)を1個のFCLコンテナに仕立てる業者のこと。不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一方向の貨物を一括して大口貨物とし、自らが荷送り人となって船社と運送契約を結ぶ業者である。航空貨物分野ではフォワーダーという。
Consignee(コンサイニー)
受荷主のこと。
Container vessel(コンテナ船)
コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、フルコン船と同義語であるが、セミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナの揚げ積み荷役方式により、LO / LO船、RO / RO船の2種類がある。
Containerizable Cargo(コンテナ貨物)
コンテナ単位で発送される大口貨物のことで、通常、荷主の責任で工場若しくは海貨業者の保税蔵置場でコンテナ詰めされる。
Container Terminal(コンテナターミナル)
コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び、一時保管を行う場所で岸壁に隣接して設置されている。
CFS(CONTAINER FREIGHT STATION)
LCL貨物の受渡し、保管、コンテナへの積み込み及び取り出し作業を行う施設をいう。
CLP(CONTAINER LOAD PLAN)
コンテナロードプランとは、コンテナ内積付表のこと。コンテナに詰められた貨物の明細などが記された書類。
CY(CONTAINER YARD)
コンテナヤード。コンテナを搬入して蔵置、受け渡しをする施設のことをいいます。また、ヤードに直接搬入できるFCL貨物を指すこともある。
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(ワシントン条約)
稀少野生動植物の絶滅を防止するため1973年3月に米国ワシントンにおいて採択された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制することにより、これら動植物の種を保護することを目的としている。
Conventional Vessel(在来船)
コンテナ船やRO / RO船など革新荷役船に対し、旧来から本船がクレーンを装備している種類の貨物船をこう呼ぶ。
C&F(COST AND FREIGHT)
物品の本船積込原価(C)に仕向地までの運賃(F)を含んだ値段、または条件のこと。貿易取引で多く使われている。
CUT
カットとは、船積貨物の受付終了日のこと。コンテナ1本単位で船積みをする場合、入港の前日に、また混載貨物の場合は入港の前々日までに指示された場所に搬入しないと船積みをしてもらえなくなる。
Custom-house broker(通関業者)
カスタム・ブローカーまたは税関貨物取扱人ともいう。貿易貨物の輸出入に関する通関手続きを荷主に代わって取扱うことを業とする者で、営業地所轄の税官庁の許可を受けたものである。海貨業者、倉庫業者、運送取扱業者が兼ねる場合が多い。
Customs Clearance of Cargo abord Barge(ふ(艀)中扱い)
輸出(入)貨物をはしけに積載したまま申告を行い、貨物について必要な検査を経て輸出(入)許可を受けることができる制度である。
Customs Examination Place(税関検査場)
輸出入貨物の検査場所として税関長が指定した税関の検査場のこと。
Customs Duty Inspector(関税鑑査官)
輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用並びに輸出入貨物に係る統計品目表の分類についての調査及び研究並びにこれらに関連する事務を担当する課長相当職の専門官のこと。
D
Dangerous cargo(危険物)
爆発物、可燃物その他人体に影響のあるものの総称。主として本船は船舶安全法及び港則法、陸上は消防法により危険物の定義及び取り扱い方法が定まっている。国際的にはIMO(国際海事機構)が定めたIMDG CODE(国際海上危険物規則)にて規定されており、日本でも、同規則を全面的に批准した「危険物船舶運送及び貯蔵規則」が船舶安全法に下位規定として制定されている。
Devanning(デバンニング)
コンテナから貨物を取り出すこと。反対にコンテナ内に貨物を詰め込む作業をデバニングという。
Delivery(デリパリー)
貨物や輸送機器の受け渡しや引渡しをいう。
D / O(DELIVERY ORDER)(荷渡指図書)
船舶会社が本状持参人への貨物の引き渡しについて、ターミナルオペレーターに指示する書類のこと。
Dimension(ディメンション)
貨物の寸法。通常、L(Length)、W(Width)、H(Height)で表される。
D / R(DOCK RECEIPT)(ドックレシート)
ドックレシートとは、船舶会社が貨物の受取証として発行する書類のこと。荷受け貨物に過不足や損傷などがあれば、ドックレシートのexception欄にその旨を記載する。ちなみにドックレシートを発行する際、貨物は輸出通関済みでなければいけない。
D / A(Documents against Acceptance)(手形引取書類渡し)
手形引取書類渡しのことで、荷為替取引における貨物引渡の一条件で、期限付荷為替の送付を受けた取引銀行が手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引渡す条件をいう。
Dray(ドレー)
コンテナを引っ張って移動させることを総称してドレージという。
Domestic Cargo(内国貨物)
本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海及び排他的経済水域で採捕された水産物のことをいう。
Dry Containers(ドライ・コンテナ)
ドライ・コンテナとは、一般雑貨を輸送するための密閉型コンテナのこと。冷凍・液体など特殊貨物以外に利用される。
E
Export(輸出)
内国貨物を外国に向けて送り出すこと。輸出の対象となる内国貨物とは本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕した水産物をいう。
E / D(Export / Declaration)(輸出申告書 / 輸出許可通知書)
貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類。税関が、輸出を許可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。
Export Declarer(Declarant)(輸出申告者)
輸出申告を行う者のことで、輸出申告者の資格には、関税法上別段の制限はなく、およそ貨物を輸出しようとする意思を有すれば足り、その輸出貨物の所有権を有するかどうかは問わない。
EDO(Equipment Despatch Order)
コンテナ機器引渡指図書。船社が荷主へのコンテナ貸し出しに際し、CYオペレーターあてに発行する指図書。これにより、バンニング場所や搬入CY、あるいは、コンテナの返却場所等が指定される。
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)
到着予定日(時間)のこと。
ETD(ESTIMATED TIME OF DEPARTURE)
出発予定日(時間)のこと。
E / L(Export Licence)(輸出承認書)
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2に掲げられている特定の規制品目(ダイヤモンド原石、血液製剤、廃棄物、核燃料物質等)を輸出しようとする場合、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて交付される。
Endoresement(裏書)
輸出の場合、輸出者がの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB / Lに流通性が出る。B / L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB / Lは無効になる。
F
FCL貨物(Full Container Load 貨物)(コンテナ単位の貨物)
コンテナ1本を単位として運送される大口貨物をいう。これに対し、コンテナ1本に満たない小口貨物をLCL貨物と呼んでいる。
Final Destination(最終仕向地)
B / Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向け地のこと。しかし、船会社の輸送責任はPlace of Delivery欄に書かれている場所までとなる。
Foreign Cargo(外国貨物(外貨))
輸出の許可を受けた貨物と、外国から本邦に到着した貨物の中で輸入が許可される前のものを、外国貨物という。単に「外貨」と呼ぶことも。ちなみに、関税法の規制の対象となる。
Formalities of Export(輸出通関)
輸出しようとする貨物を港周辺の保税地域に運び込み、税関に申告して許可を受ける一連の税関手続をいう。
Forwarder
運送業者のこと。
FOB(Free on Board)(本船積込渡し条件)
貿易取引条件のひとつで、輸出サイドの本船渡し条件の積み価格のことをいう。受け荷主側が運賃、保険料を支払い、船積み決定権がある。
FREIGHT(海上運賃)
海上輸送費に荷役料を加えたものが、海上運賃となる。
Free Time(貨物の無料保管期間)
揚港におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。
G
GRI(General Rate Increase)(海上運賃一括値上げ)
海運同盟が、海上運賃タリフ(tariff)を全品目一律値上げすること。これには、日本荷主協会との事前協議が必要である。
GSP(Generalized System of Preferences)(一般特恵関税制度)
開発途上国からの輸入貨物に一般よりも低い関税率を適用し、それによる開発途上国の輸出所得の増大、経済発展をはかるための制度。
G / L(Gross Weight)(総重量)
風袋(外包装と内包装)込みの総重量のこと。
H
Harbor Transport Operetor(Intermediaries of Operator)(乙仲)
乙仲(おつなか)とは港湾荷役業者の一種。乙種海運仲立人の略称。船舶の売り主と買い主の間に立ち、契約の出合い付けや、荷主の依頼による貨物の積み込みや陸揚げ作業などを行う。
HAWB(House Air Waybill)(運送状)
混載業者が自己の運送約款に基づいて、荷主との運送契約を締結時に発行する運送状のこと。
保税展示場(Hozei Display Area)
保税地域の一種。国際的な博覧会、見本市などにおいて、外国貨物である展示物品を関税未納のまま展示、使用できる場所。
Hozei Manufacturing(保税工場)
保税地域の一種。施設の所有者が自らの事業として、外国貨物を関税未納のまま加工、製造できる場所。
Hozei Warehouse(保税蔵置場)
平成6年の関税法の改正で、従来の保税上屋と保税倉庫が統合されてできた保税地域の一種。施設の所有者等が自らの事業のために利用するもので、外国貨物の積み卸し、運搬、蔵置ができる場所として、政令で定めるところにより税関長が許可したもの。
I
Import(輸入)
外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう。
IC(Import Consumption)(輸入申告)
輸入申告のこと。本船、はしけ又は上屋から直接輸入することである。
Import Declarer(輸入申告者)
輸入申告を行う者のことで、輸入申告者は現実に貨物を輸入しようとする者であればよく、その貨物の所有権の有無は問わない。
ID(Import Declaration)
輸入申告書のこと。
(IS)Import for Strage(蔵入)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に外国貨物を入れ又は置くこと。
IM(Import for Manufacturing)(移入承認申請)
移入承認申請のこと。保税工場において、外国貨物を保税作業に使用すること又は保税工場に貨物を置くことについて税関長の承認を受けて、貨物を入れ又は置くことである。
IBP(Import Permit of the Goods Delivered Before Permit)
輸入許可前引取りをした貨物の輸入許可のこと。本許可ともいう。
(ISW)Import from Storage Warehouse(蔵出輸入)
保税蔵置場にある外国貨物を輸入すること。
IMW(Import from Manufacturing Warehouse)(移出輸入申告)
保税工場にある外国貨物を輸入することである。
Import Quota Certificate(輸入割当証明書)
Indication of the Country in Origin(原産地表示)
特定商品の出所を表示し、その商品の出所又は品質を保証することを直接の目的とする標識のこと。
Integreted fowarder(総合物流業者)
輸送、保管、荷役、梱包、情報など物流全体に関する施設、機能を保有し、顧客の需要により陸、海、空に渡る国内、国際間における一貫した物流サービスを提供する業者。
Intermediate Trade(仲介貿易)
日本の商社が外国間に立って仲介する貿易取引のこと。この際、日本商社は契約の当事者として貨物を輸出国から輸入国へ移動させ、その際に発生する差額を手数料として入手する。
Invoice(送り状)
Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にInvoiceという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもInvoiceをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。
L
Lashing(ラッシング)
ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。
L / C(Letter of Credit)(信用状)
輸入者の依頼で、銀行が発行する荷為替信用状の事で、船積書類の提示、輸出入手形に対して、発行銀行が商品代金の支払いを保証する。
LCL貨物(Less than Container Load 貨物)(コンテナ一本に満たない小口貨物)
コンテナ一本分に満たない小口貨物をいう。
L / G(Letter of Guarantee)(保証状)
債務者が債権者に差し入れる保証状のことである。輸入取引の際に、本船入港までに船積書類が未着の場合は、船会社所定の書式に所要事項を記入し署名したものと、銀行所定の輸入担保荷物保証依頼書に必要書類を添付して、銀行と連署した保証状の交付を受け、これをB / Lに代えることができる。
Lighter,barge(はしけ・艀)
港湾において、主としてブイに係留中の本船と物揚場や水際線に面する倉庫、荷揚場間の貨物輸送に従事する港運船。重量物の荷役においては、岸壁係留中の本船への揚げ積みなども行う。狭義には引船により曳航されるものを指すが、広義には自航式のものも含む。
M
Manifest(積荷目録)
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B / LNO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。LCLの場合は、コンテナにされている小口貨物の明細となる。輸入申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。
M / R(Mate Receipt)(船積受領証)
船舶の船積責任者(通常は一等航海士)が船積指図書(S / O)に基づく船積みを完了したときに発行する証書のこと。
MASTER B / L(船社船荷証券)
船舶会社が発行するB / Lです。HOUSE B / Lが発行されるときに区別するためにMASTERと付けていますが、HOUSE B / Lが発行されないときは通常のB / Lと同じもの。
MAWB(Master Air Waybill)(運送状)
混載業者が混載貨物を取り扱う場合、混載貨物を1件の大口貨物として航空会社に搬入する時に代理店を通じて航空会社が発行する運送状のこと。
M3(立法メートル)
Cubic Meter。立方メートル
N
NACCS(Nippon Air Cargo Clearance System)(航空貨物通関情報処理システム)
昭和58年8月から新東京国際空港と同物流基地(TACT)で導入。昭和55年10月には大阪国際空港に拡大。東京、中野の航空貨物情報処理センターのコンピュータと税関、航空会社、銀行、フォワーダー等をオンラインで結び、通関及び関連業務を自動処理するシステム。
Notify Party(着荷通知先)
B / Lに記載されている項目で、揚げ地おける貨物の到着通知先のこと。
NVOCC(NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER)
本来、B / Lを発行できるのは船舶会社に限られていますが、NVOCC業者は船を所有しないにもかかわらず、B / Lを発行することができる。このような業者を利用運送業者といい、国土交通省の認可を受けて事業を展開しています。また、利用運送業者の発行するB / LをHOUSEB / Lという。
O
OrderB / L(指図式船荷証券)
特定荷受人を記入しないで、"to order"又は"to order of ~"のように荷受人又はその指図人に荷渡しすべきことを記載している船荷証券をいい、流通船荷証券のことである。この船荷証券は転々と流通することができ、その所有権は白地裏書によって移転される。そのため、裏書きされた船荷証券を善意に取得した者は当該船荷証券上の所有権を取得するとともに、貨物の所有権も取得できる。
OAT(Over Air Transport)(保税運送)
空路による保税運送のこと。
OLT((Bonded)Overland Transport)(保税陸上運送)
日本国内の運送保税の一種で、外国貨物を指定保税地域から指定保税地域まで陸上運送することをいう。
Ocean B / L(船荷証券)
外国貿易船によって外国の港を仕向港とする国外運送について発行される船荷証券。
P
Packing List(包装明細書)
パッキングリスト。包装明細書のことです。貨物の梱包形態やケースマークなど、貨物に関する様々な情報を記載している。
Packing style(荷姿)
貨物に施される外部包装の形態をいう。
Place of Delivery(荷渡地)
B / Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。
PCS(Port Congestion Surcharge)(船混み割増料金)
パレット単位による梱包方法一つで、カートンや小型包装貨物などの集合包装に用いられている。フォークリフトで作業できるため、大きく重い状態でも移動等が容易になる。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類上ではP / Tと省略することもある。
Place of Receipt(荷受地)
B / Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。
PCS(Port Congestion Surcharge)(船混み割増料金)
特定の港が荷役中の船で混み合う(船混み)と、滞船が長期化し、それにより発生する割増料金(料率)のこと。
Port of Discharge(揚地港)
B / Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。
Port of Loading(積地港)
B / Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。
Prohibited Articles(輸入禁製品)
国家が社会公共の衛生、風俗その他公益の侵害を防衛する見地から法律によってその輸入を禁止している物品のこと。
R
Re-ship(積戻し)
外国から我が国に到着した貨物を陸揚げ又は取卸しののち、輸入手続を経ないで外国貨物のまま保税地域から再び外国に向けて送り出すこと。税関に対して積戻申告書を提出し、その許可を受けなければならない。
RR(Rate Restoration)(運賃修復)
市場における実勢の海上運賃が海上運賃タリフ(tariff)を下回った場合、実勢レートを引き上げ、本来適用されるべきTariffに近づけると言う意味と、以前のLevelから下がってしまった実勢レートを元のLevelに引き上げると言う意味の両方で使用されている。
S
S / A(Shipping Advice)(船積案内書)
貨物の船積み完了後、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する書類の一つで、注文番号、品名、数量、金額、船名、出港日、B / L NO、など、船積みの明細が書かれている。
SEA-NACCS
当初、航空貨物を対象にスタートしたNACCSの海上貨物版です。1991年から税関、通関業者、銀行の三者でスタートし、1999年から船舶会社、海貨業者、保税地域(CYオペレーター)も加わった。
SEA Waybill(貨物運送状)
流通性の無い運送証券。運送業者(船会社)から貨物の引き渡しが受けられる。
Shed(上屋)
物品を一時的に仮置するための施設で、港湾におけるものは、輸出入貨物を搬入し、輸出入通関及び一時保管を行う。他人から寄託を受けた貨物を保管する倉庫とは異なる。
Shipper(荷送人)
荷送人又は荷主のことを指し、Consignorともいう。運送人と運送契約を締結する当事者。
Shipping Documents(船積所類)
船荷証券、保険証券、インボイス、包装明細書、原産地証明書等をいう。
Shipping Mark(荷印)
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
S / O(Shipping Order)(船積指図書)
荷主から船積み申し込みを受けた船社が、本船船長に対して当該貨物を船積みすることを命ずる書類。荷主(多くは代理人)は、本船船組みの際にこれを本船に提出し、船積みが行われる。
Shoring(ショアリング)
木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。
S / I
船積依頼書のこと。
Skid(スキッド梱包仕様)
裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法の一つで、貨物の下に角材などでゲタをはかせる様式。貨物を保護するものがないため、コンテナ内の積み付けには十分な配慮が必要。書類上ではS / Dと省略することもある。
Surveying(検数)
輸出入貨物について、輸出入業者に代わってその商品の個数、重量、損傷度合い等を判定し、その証明を行う業務のことで、検数業務に従事する人を検数員といい、タリーマン、チェッカーとも呼ぶ。 →タリーマン
T
Tariff or Rate of Duty(税率)
課税標準に対して適用される税額を計算する率のことをいい、価格を標準として課せられる税率を従価税率、数量を標準として課せられる税率を従量税率、この両者が選択又は併課される税率を従価従量税率という。
THC(TERMINAL HANDLING CHARGE)
コンテナ取り扱い料金のこと。コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を、船舶会社が荷主に課金する料金のことです。THCは積港と揚港の両方で発生する。
THROUGH B / L(通し船荷証券)
通し船荷証券のこと。依頼のあった運送の一部を下請け運送人に履行させる場合に発行されるB / Lを、THROUGH という。
V
Vanning(バンニング)
コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出すことをDevanningという。
W
Warehouse(倉庫)
貨物を長期保管する施設。普通倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫などの種類がある。市内倉庫の大部分は、臨海6区に立地している。
WAYBILL(貨物運送状)
通常「船荷証券」といわれるB / Lとは違い、WAYBILLは単に運送状としての役割しか持ち合わせていない。そのため、これを提示することなく船舶会社から貨物の引き渡しを受けることがでる。B / Lが発行されている場合、「輸送中に紛失した」「輸入者への到着遅延などにより貨物が到着しているのに、貨物を引き取ることができない」など、何かとトラブルが発生することがある。この際、B / Lなしで船舶会社から貨物を受け取ろうとすると、銀行保証状を入手する必要があるなど手間がかかることに。その点、WAYBILLは貨物が到着次第、荷受人がWAYBILLを提示することなく、貨物を引き取ることができるのが特長。
Y
YAS(YEN APPRECIATION SURCHARGE)(円高損失補填料金)
アジア関係同盟・協定がCAFに替えて導入した料金。急激な円高による損失を補填する割増料金ともいえる。指定された期間において、平均為替相場が1ドル120円を超え円高になった場合に課金されることになっている。